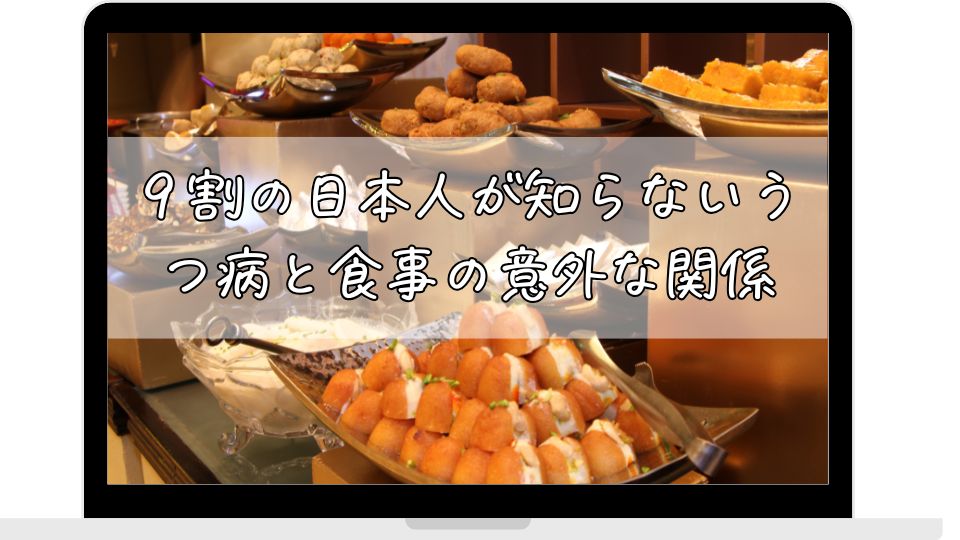この講義では、うつ病と食事の関係、精神科病院の役割、訪問診療の重要性、東洋医学における発酵弁償、甘いものの摂取と鬱病の関係について議論されました。特に、糖類の過剰摂取が腸内細菌の炭素脂肪酸の生成を妨げ、鬱傾向を引き起こす可能性があることが指摘されました。また、精神科病院での食事管理やDSMと精神医学の薬の処方についても触れられました。
要点
- うつ病と食事の関係
- 精神科病院の役割
- 訪問診療の重要性
- 東洋医学における発酵弁償
- 甘いものの摂取と鬱病の関係
- 炭素脂肪酸と腸内細菌
- 甘いものの歴史と文化
- 高血糖値スパイクと感情の起伏
- 精神科病院での食事管理
- DSMと精神医学の薬の処方
ハイライト
"甘いものを食べるとドーパミンが出るわけですから麻薬のようなものなんですね。""私は明らかに狂ってました。おかしかったです。やめてしまったら全然そんなに欲しくない。"
章とトピック
うつ病と食事の関係
うつ病は甘いものの摂取と関連があり、特に糖類の過剰摂取が腸内細菌の炭素脂肪酸の生成を妨げ、鬱傾向を引き起こす可能性がある。
- 要点
- 甘いものを摂取するとドーパミンが一時的に増加し、多幸感を得られるが、その後血糖値が急激に変動する。
- 高血糖値スパイクが感情の起伏を激しくし、鬱病のリスクを高める。
- 留意点
- 甘いものの摂取を控えることがうつ病の予防に繋がる可能性がある。
精神科病院の役割
精神科病院はうつ病だけでなく、統合失調症や認知症、アルコール依存症、薬物中毒などの治療にも重要な役割を果たしている。
- 要点
- 精神科病院の病床数が多いことが国際的に人権侵害とされ、患者を家庭に戻す圧力がある。
- 訪問診療を通じて患者の生活状況を把握し、適切な治療を行うことが重要。
- 留意点
- 患者の生活環境を理解し、適切な食事指導を行うことが重要。
現代の精神医療と東洋医学の違い
現代の精神医療は症状に対して薬を処方することが多く、東洋医学的な思想や食事の影響が考慮されていない。
- 要点
- 統合失調症の症状に対する薬の処方
- 東洋医学的な思想の欠如
- 食事の影響が考慮されていない
糖類の過量摂取と精神疾患の関係
糖類の過量摂取が鬱病などの精神疾患に影響を与える可能性がある。
- 要点
- 糖類の過量摂取が多い
- 甘いもの依存症の原因
- 精神疾患との関連性
食事と鬱病の関係
食事の内容が鬱病の発症に影響を与える可能性がある。
- 要点
- 甘いものの摂取と鬱病の関係
- 食物繊維やビタミンCの摂取方法
- 日本の伝統的な食事の重要性
甘いもの依存症の原因と影響
甘いもの依存症は脳の快楽報酬系に影響を与え、精神的な健康に悪影響を及ぼす。
- 要点
- 脳の快楽報酬系の影響
- 戦後の食文化の変化
- 社会的な影響
日本の戦後の食文化の変化と健康への影響
戦後の食文化の変化が日本人の健康に影響を与えている。
- 要点
- GHQによる食文化の変化
- チョコレートの普及
- 社会的な健康への影響
鬱病予防のための生活習慣
鬱病を予防するためには、伝統的な日本の生活習慣を取り入れることが重要である。
- 要点
- お風呂に入る習慣
- 低体温の改善
- 人間関係の構築
低体温と健康の関係
低体温は健康に悪影響を及ぼす可能性があり、入浴によって改善できる。
- 要点
- 低体温の影響
- 入浴による改善
- 水温の高いお風呂の効果
お風呂の水圧と体の老廃物排出
お風呂の水圧が体の老廃物の排出を促進する。
- 要点
- 水圧の効果
- 老廃物の排出
- 体温の上昇
鬱病のプロファイリング
鬱病の発症には特定の条件が重なることが多い。
- 要点
- 甘いものの過剰摂取
- 低体温
- ストレス要因
人間関係と精神健康の重要性
人間関係の構築が精神健康の維持に重要である。
- 要点
- 友人や親友との関係
- ストレスの共有
- 精神疾患の予防
全文は以下
日本の病を治す吉野俊明です。今回はうつ病と食事の関係についてお話をしたいと思います。私はですね、2011年から2013年まで精神科病院の理事長をしていました。そこの病院は実はうつ病が専門なんですね。認知症とか統合失調症の人はいなくはありませんでしたが、少なかったです。ここは250床のある大きな病院で、随時ですから約200人ぐらいはうつ病の患者さんが入院していました。
この精神科病院の話になるとちょっと政治的に長くなってしまうんですが、実は日本は世界で一番精神科病院の病床っていうのが多いんですね。これも国際的な圧力によって人権侵害なんだと。病院に閉じ込めておくのはおかしいということで、どんどんどんどん家に戻しなさいっていうのが国際的に圧力をかけられてるんですね。イタリアなんかは、精神科病院っていうのはなくなっちゃったぐらいなんですね。ただ精神科病院の役割っていうのはうつ病だけじゃなくて、統合失調症なんかももちろんそうですし、認知症もそうなんですけども、アルコール依存症だとか、薬物中毒っていうのもあるので、こういう人たちっていうのはちょっと入院しないと難しいところもあるわけですよ。
なので僕は何が何でも精神科病院を全部なくせっていうのは意見は賛成しかねますけども、ところがなるべく患者さんを戻せと言ってる中で、当時私が考えたのは訪問診療の舞台を作るということで実際作ったんですね。精神科病院で入院していたうつ病の人っていうのを一時帰宅させて、訪問看護でどうなってるんですかって問診を取りに行ったりとか、どんな食事してるんですかっていうふうにやるわけですよね。僕は歯科医師ですけども理事長になっていたので、精神科病院にいるときは本当に病棟を全部回って、皆さんの意見を聞いて、寒くないですかとか、暑くないですかとか、エアコンがうまくいってますかとか、テレビ見れてますかとか、体調どんなですかとか、ちゃんとかめてますか、飲み込めてますか、ご飯どうですかっていうのを聞いて。
経営の改善をするためにそういう話もしてたんですね。訪問看護部隊ができた時もついて行って、退院して自宅にいる人たちを見ていくわけです。そこで会話みたい、いろんな事実があります。それは後でゆっくりお話します。鬱病というものは一体どういう病気なんでしょうか。一体誰がなるんでしょうか。誰にでもなる病気なんでしょうか。それとも雷で撃たれたように突然なってしまうような病気なんでしょうか。それは違います。東洋医学の病気のなり方の分類というので、
発酵弁償というのがあります。これは以前もお話ししたことがありますけども、まず体力がある人、体力がない人、体温が高い人、体温が低い人。これで4つ軸が分かれますね。さらに表症、理症、表に出る、裏に出るという分類があるんですけども、ここでは割愛します。鬱病になるような人っていうのはどういう人かというと、当たり前ですけど、実症ではないです。実症というのは、例えばプロレスラーとかお相撲さんとかそういう人がいる。体力もあって、記録もあって、勇気もあってというような方ですよね。巨匠というのは書いて字のごとく巨弱体質な人ですよね。体温が高い方なのか低い方なのか。結論から言うと体温が低い方です。巨匠で体温が低い側の人というのが鬱状態になりやすい人なんですね。巨匠で体温が低い人だったら誰でも鬱病になるのかといったら決してそんなことはないわけですよ。
愛する人が死んじゃったとか、愛するペットが死んじゃったとか、突然首を言わだされたとかってそういう社会的な条件もありますよ。条件もあるんですけども、それだけでもならないわけです。この大きな要因の一つに甘いものをたくさん摂ってるか摂ってないかっていうのを見ていくんですね。その人の巨症か実症か体温が高いか低いのか甘いものをたくさん摂めてるか摂めてないかっていうのは東洋医学的な見方なのです。西洋医学的にも正当性があります。というのは甘いものをたくさん、糖類をたくさん摂ってると炭素脂肪酸っていうものが腸内細菌が作らなくなってくるんです。炭素脂肪酸。
というものが少ない人ほど鬱傾向になることは分かってるんですね。西洋医学的にもそうですし、東洋医学的にもそうだと。例えば、愛する人が誰か亡くなってしまったら夫が亡くなったとか、妻が亡くなったとかね、もっとかわいそうだったらお子さんが亡くなったとか、それでもその悲しさのあまりですよ。もともとの巨匠のお母さんが、体温が低い人がそういうことがあって悲しいと、食欲がないと、菓子パンばっかり食べてるというふうにすると、どんどんどんどん鬱状態がひどくなっていってしまうわけですよね。
甘いものを食べるっていうのはどういうことかっていうとですね、糖類を摂ると最初の15分間ぐらいはやっぱりドーパミンっていうのが出て、多効感が出るんですよ。悲しくなった時とか疲れた時とかに甘いものが食べたくなるというのはこのことなんですね。ところが、これは現代だからできることであって、縄文時代にお砂糖っていうものがあったのか、蜂蜜っていうものがあったのかっていうとないんです、これはね。じゃあ果物はあったのか。果物ありました。
サトウヒビというものはありましたよね。ベトナムとかタイが原産で絞って生成して煮てですね、白いお砂糖にしていくってことですよね。それからハチミツね。ハチミツも例えば蜂の巣はあります。それこそヒグマが蜂の巣を食べたりとかします。そういうものはあったんですけども、蜂の巣を取ってきてということを大量にするためにはどうしたらいいかって言ったら養蜂をしなきゃいけないわけです。で、蜜蜂を飼って飼いならして刺さないようなおとなしい種類にして人工的に吹き出しを抜くみたいにしたものを延伸分離器に入れてハチミツをたくさん作ってそれを食べる。
これをやっていたのはさあ誰なんですかっていうと、実は西暦200年から300年ぐらいのローマ帝国ではやっていました。皇帝たちが甘いものを食べたいからなんですね。ハチミツっていうのの取り方っていうのは実はアジアではほとんどしていなかった。なぜならば里芋が食べたりとかさつまいもが取れたり。それこそサトウキビが南の方では取れるのでわざわざ蜂を養殖してまでするっていう。文化っていうのが東南アジアにはないんですね。自然の中にある甘いものっていうものを食べるっていうのはあったんですけども、
例えばイチゴを皆さん考えてください。昔のイチゴって私もそうでしたけど、子供の頃食べるときって言ったら、もうそれだけだったら酸っぱくて食べられなくて、イチゴを潰すなんかそういう専用のスプーンがあって、牛乳を入れて砂糖を混ぜたりとかね、あるいはグレープフルーツなどもそうでした。砂糖を乗っけてこうほじくり返して食べていたわけですけど、今は普通に美味しいでしょ。イチゴでね、だいたい糖度で17倍から18倍ぐらい上がってるんですよ。それが僕が5歳児から今55ですけども、50年間だとすると、それをさらに50年前はどうなんだ、さらに50年前はどうなんだってずっといくと、
我々が考えているような甘い果物っていうのは違うんですね。もうほとんど野菜に近いようなものだった。柿ですらそうですよ。私が子供の頃顔を向いていた柿なんかっていうのはそんなに甘くなかったんですけど、今のはもうびちょびちょに柔らかくて甘くなってる。昔の日本人が食べていたっていう、そういう甘いものっていうのは食べてないわけですよ。のイチゴを食べてくるとか、秋になるとか、カキを食べるとかそういうものがあったわけですね。スイカですが西暦1400年ぐらいのスイカっていうのが原種でこのぐらいの大きさしかなかったんですね。で割ると中赤いとこないんです。もともとあれはキュウリの仲間ですから野菜ですよね。真っ白でほんのちょっとだけ周りに赤いとこがあったのをそれを数百年かけて500年ぐらいかけて今のスイカにしたわけですよね。
2000年ぐらい前古墳時代とか弥生時代とか縄文時代に今我々が食べてるような甘い果物があったかって言ったら当然ないわけですよね。砂糖みたいな生成した白いお砂糖みたいなものは絶対ないわけですよ。ということはその時代っていうのはそういう鬱病がないわけですね。当たり前ですよね。鬱病のライオンとか鬱病のゾウさんとかの鬱病の野良猫ですらいないわけですよ。人間がやっぱり人工的に糖類っていうものを作ったと。甘いものを食べるとドーパミンが出るわけですから麻薬のようなものなんですね。これはね。甘いものの歴史もお話しすると長くなりますけどもこの甘いものとコーヒーを組み合わせて甘いコーヒーっていうものを作るとカフェインが出て眠らなくても済む。甘いものがあるから欲しいということで西洋では。
産業革命の時代に甘いコーヒーを飲ませておけば奴隷が働くっていうためにこういうものを作られたっていうこういう歴史があるぐらいなんですね。もともとは糖類で鬱病になるっていうことが非常に少なかったわけですね、昔はね。体質が巨小で体質が体温が低かったとしても鬱病になりにくいようなそういう社会的な状況だったわけです。これが戦後GHQがギブミーチョコレートっていうぐらいですね、子供にチョコレートをトラックに山積みにして配り歩いたわけですよね。甘いものっていうものに我々は目覚めてしまったわけですね。
この悲しくなった時にドーパビンが出るこの甘いものね、チョコレートを食べたりとか甘い果物を食べたりとかすると多幸感が得られますが、血糖値が急激に上がりますのでインシュリンっていうホルモンが出てドーンと下げます。例えば血糖値が120ぐらいの人がチョコレートを食べたりすると一時的にはですよ、私もずっと指につけて測ったことあるんですけど、もう200何十、250とか60ぐらい平気でいきます。その瞬間にインシュリンが出るとドーンと下がると、もう60とか50、50ぐらいまで下がると下がりすぎるので今度はグルカゴンとか、コルチゾールっていうホルモンが腹筋から出て血糖値を上げ直すんですね。
この時のグルカゴンとかコルチゾールとか出てる時がイライラとか不安だとかやる気のなさとかが出てくるんですよ。で、それを消すためにまた甘いものを食べるっていうのが高血糖値スパイクって言うんですけども、甘いもの依存症になって感情の起伏が激しい人ができていって免疫力が落ちていくっていうことが起こるんですね。鬱になるのに先ほど言った東洋医学的なことに加えて、社会学的に戦後日本人が甘いものを大量に食べる習慣づけされてしまったっていうものも入ってくるわけですね。
それからこれが脳の快楽報酬系といって、麻薬と全く同じ回路に砂糖が入ってしまう。なので私がその精神科病院の臨床をやってる時は、全部基本的には手作りの料理を出していました。多くの病院がコッペパンが出てきて、ヨーグルトが出てきて、みかんが1個出てきて、ハムエッグが出てきたりとか平気でやるわけですよ。そういうものを私は絶対にやめていたので、野菜を買ってきて、例えば白菜買ってきて、人参買ってきて、お肉を買ってきて、ちゃんと調理して、私もそれも毎日食べてました。味見をして、で、喧嘩がどのぐらいなんだってこともありますしね。そうやって食べていってとっても美味しかったです。そうやってうつ病で入院していた人がちゃんとしている病院食を食べていくと、回復してくるんですよ。もちろん薬も使えますよ。そういう人たちが先ほど言った理由で一時退院するわけです。
病院の中では、当然こんな甘いものがうつ病にいいんですよっていうそういうことは社会的にも認知されていないし、精神科医もそんなことをほとんど気にしていません。訪問看護に僕は行って、驚愕の事実を見るわけですよ。一番びっくりしたのは、当然生活保護を受けているので非常に狭いアパートに住んでいるんですけども、どう元気にやってるのって書いてて、ちょっとトイレ貸してくださいって言ったら、ものすごくトイレが臭いわけですよ。もうケトン臭がするわけですよ。糖尿病の人のおしっこの匂いがする。これは甘いものを食べてるなと思って。何食べてるんですか?冷蔵庫をガバッと開けたら、コーヒーゼリーが20個ぐらい入ってるんです。なんでやってるんですか?って言ったら、コーヒーゼリー大好きでいくらでも食べられるんです。もっと他にちゃんとお肉を食べてるんです。
私はこれでいいんです。コーヒーゼリーに下のところにカチャンとやるとコーヒーフレッシュが入っていて、カチャンとやるとガムシロップがあって、それをかけてクラッシュして、それで暮らしているわけです。吉野院長も精神科病院の臨床やってましたからね。これしかないんですけどどうぞと。愕然としましたから。それでまた戻ってくるわけですよ、重症化して。こういうことを訪問のナースとかに丸投げしてて、ちゃんと薬飲んでるかどうかってやってちゃダメなんですよ、やっぱりね。どんなものを食べていて、トイレにがどんな匂いをして、ちゃんとお風呂に入ってるか入ってないかとかね。そういうことをやること自体が本来であれば、それはだからちゃんと注意の治療になるわけですよ。
肺の治療っていうのは抗生新薬を出すだけ。注意の治療っていうのはその人が何を食べてるかってことも見ていくわけです。ちゃんと食事指導をしなきゃいけないんだっていうのは僕はだからこれが本当に確信に変わった瞬間でした。現場で見るってとっても大事なことなんですね。患者さんから聞くだけじゃなくて生活の中に入り込めるわけですから、訪問看護の経験、訪問看護っていう会社を立ち上げたっていう経験は私にとってとっても大事な経験でした。広がって、そこの病院は私の勤務。戻って自分で開業して精神科医の先生も入ってもらってうつ病の治療をしていました。やはりですね症状を聞いて薬出してるだけなんですよ。これはなぜかというとですねDSMっていうそういう分類があるんですね。アメリカの精神科の学会が作ったDSM1から今5、6になってるのかなあるんですけども当初何で作ったかというと朝鮮戦争の時にそのアメリカ軍がですね兵士に対して虐殺を命じたりするので。
アメリカに本土に戻ってくるとですね本当に頭がおかしくなっちゃってるんです。それで眠れない人だとか多重人格になったとかうつ病になったとか統合失調症になっちゃったとかっていうのを分類して一体どんな薬が効くのかっていうのをやってたんです。それがベトナム戦争でさらにバージョンアップされたんです。それをこういう症状の時にはこの薬が効くと。例えば本来であったら命じた情感が悪いとか子供を殺せとかって言ったこと自体がいけないんですけどもその原因はどうでもいいと。今ある症状に対してどんな薬が効くのかっていうと。
いったことを一般の人にも使い出したっていうのが近代の精神医学の薬の処方の原点なんですね。私はだからその精神科病院行ってる時も精神科医たちが一生懸命こんな分厚い本なんだと見てるわけですよね。どの症状にあってるのかな。例えば睡眠障害っていうところを見ると、例えば入眠できない。あるいは入眠できたとしても何回も覚醒してしまうとか。早期覚醒で早く起きてしまうとか。その場合は何とかの薬だ。いくら読んでもですね、なんでそういうふうに眠れなくなったかっていうのは書いてないんですよ。
でも現代の精神医療っていうのはこれで行われちゃってるわけですよね。例えば統合失調症であれば、厳重があると、悪口を言ってると、机をバンバン叩いてるとかこうするとか、かかってこないんだけど電話がリンリン鳴ってるからとかね。あるいは何が見えるとか。だったらこういう薬ですよねっていうふうになっちゃってるわけですよ。全然東洋医学的な思想ですとか、何を食べてるかっていうのが入ってきてないわけですよね。僕は10年ぐらい前に、おそらくこういうのが原因だっていうのが分かった。それからうつ病になってる人たちですね。食事の問診取ってる。やっぱり糖類の過量摂取が絶対多いんですよ。
例えばこういう言い方をします。私はちゃんと毎日ヤクルトを飲んでます。なんで飲んでるんですか?これは乳酸菌を得て腸にいいからです。そうですか?私は必ずチョコレートを食べてます。なんでなんですか?ポリフェノールが体にいいからなんです。あ、そうですか?私は必ず喉が痛くなったら喉がめを舐めてます。これで喉の調子がいいんです。というわけですよね。例えば乳酸菌を取るんだったら納豆でもいいでしょ?ぬか漬けてもいいんじゃないですか?ポリフェノールを取るんだったら日本茶を飲めばいいんじゃないですか?喉がおかしいのに喉がめにしないで。
硫黒酸にすればいいんじゃないですか?というと絶望の表情をするんですね。それじゃ甘いものが何にも取れないじゃないですか?ほら言ったという話になるんですね。食物繊維を取るため、ビタミンCを取るために,バナナを選んでしまうんです。バナナは実は糖度が35万点。チョコレートぐらいに糖度が高いですね。さつまいももそうなんです。さつまいもは焼き芋にすると糖度が65万ですね。明らかにケーキよりは甘いぐらいなんですね。自然のものだからとか、果物だからとか,スイカのように野菜だからだ、ポリフェノールなんだと、腸内細菌よくするんだとかいうふうに言って、その中から甘いものを摂るように摂るようにっていう中毒になっちゃってる状態が鬱病なんです。先ほど言ったように巨症っていう体質を実症に持っていくっていうのは極めて困難です。巨弱体質な人もプロレスラーになるってのはできませんよ。でも低体温の人を高くするっていうのは入浴でかなり改善します。水温の高いお風呂に入るようにすると改善します。
そして甘いものどうして依存症になっちゃってるのかっていう話を脳の快楽報酬系というところで説明します。そして最後に言うのは日本が戦争に負けたのでGHQがチョコレートというものなどを対応に持ち込んできて、これでなったっていう戦争で負けてしまったんだっていう話になってくると、皆さん話を聞いてくれるんですよ。ある意味自分もその犠牲者なんだと。そのレベルになってくると社会を治すっていう話になってくるんで、上位っていう考え方が出てくるんですね。この甘いもの中毒から抜けてた人たちはこう言います。私は明らかに狂ってました。おかしかったです。やめてしまったら全然そんなに欲しくない。
いろんな理由をつけてきて甘いものを摂ろうとしていたのかと。乳酸菌を摂るためですとかポリフェノールを摂るためですとか腸内細菌を良くするためですとか食物繊維を摂るためですとか。別に食物繊維はごぼうで摂ったっていいんですよ。わかめで摂ったっていいんですよ。ビタミンCもそうですよ。ビタミンCだって日本茶だって摂れますから抹茶にすれば良いわけですね。いろんな方法があるのでそうすると抹茶を飲んだりお茶を飲んだりとかごぼうを食べたりとかすることって言ったら結局昔から日本人が食べてる食事だったんですよ。そこが鬱病にならない生活習慣があったと。最後にこれは1999年ぐらいに鬱は心の風であるっていうキャンペーンが出されたっていう時代がありました。これによって抗精神薬が2兆円から3兆円ぐらいバーンと市場が広がったんですね。精神疾患の患者さんのリセプトはなんと65倍も増えた。
このキャンペーンだけで産業を一つ作ることができたんですね。こういうこともあったんですよ。こういういろんなことによって鬱の患者さんというのが非常に増えてる。でも冷静に見ればですよ。昔古来の考え方をしていると。まずならない。それからもしなるんであれば、なので、低体温の人。低体温の人も実はうんと日本人は少なかった。毎日お風呂に入っていたからなんですね。お風呂もこういう寝風呂じゃなくて、五重門風呂までは言いませんけども、それこそ文化住宅なんて古い言葉なんですけども、膝を抱えて入るようなお風呂っていうのは、今のお風呂よりも2倍ぐらい水深があるんですね。
それだけ水圧がかかるわけですよ。水圧がかかっている状態だと、体の老廃物っていうのがギュッと、例えばふくらはぎとか押されて、これが腸脈に入って、お風呂に入るとおしっこしたくなるっていうのは、裸になったからとか寒いからじゃなくて、水圧がかかるわけですよ。そうすると体の中に入っている老廃物をちゃんと捨てると、毒素をちゃんと抜くと、それからご飯に昔は食べていたと、それがシャワーだけになっていて、お風呂にも入らないと老廃物は抜けない、体温は低くなる、そして甘いものを食べると、そして私は巨匠であると、こういう条件が重なったときに、誰かが亡くなったとかいじめられたとかって言って、うつ病になっていく。こうやってプロファイリングしていくと、外れたことがないんですよ。
もし皆さんが、もし落ち込んでいるときにね、ケーキのどか食いとかをすると、そういうのがうつ病のきっかけになってしまう。お菓子を食べたりとか清涼飲料水を飲む前に 友達とか親友とかに実はこんな悲しいことがあるんだとかって言ってもらう そういう人間関係を作ったりすること自体が こういう病気の予防につながるということなんですね。今回はうつ病と食事の関係についてお話をさせていただきました。日本の病を治す吉野俊明でした。