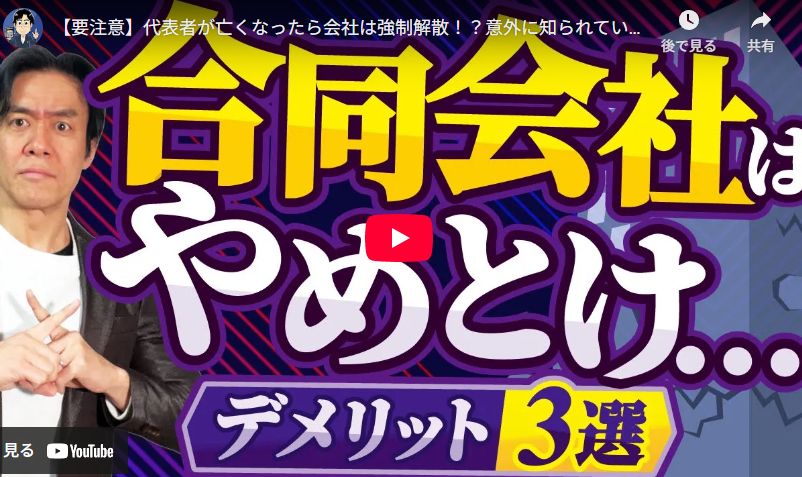テーマ
株式会社と合同会社の比較、特に合同会社の意外に知られていないデメリット3選
要点
株式会社と合同会社は税金の計算方法が基本的に同じだが、設立コスト、信用力、意思決定方法、役員の任期、株式公開、決算広告義務などで違いがある。合同会社には主に「一人一票の完全合議制」「非常勤役員の概念がない」「社員(役員)の死亡は退社扱い」という3つのデメリットが存在する。これらのデメリットを理解し、自身の事業計画や将来の展望に合わせて最適な会社形態を選択することが重要である。特定創業支援等事業を活用することで、設立コストを大幅に削減できる特例もある。
ハイライト
合同会社は特定創業支援等事業を活用すれば、登録免許税が半額となり、最低3万円で設立可能である。しかし、複数人で設立する場合、合同会社の「一人一票の完全合議制」は意見対立や実質的な会社乗っ取りのリスクをはらむ。また、「非常勤役員の概念がない」ため、配偶者などを役員にしても社会保険加入が必須となり、所得分散による節税対策が難しくなる。さらに、「社員(役員)の死亡が退社扱い」となるため、一人会社では会社解散、複数会社では相続人が経営権を持てず、出資の払い戻しのみとなるリスクがある。これらの問題は、定款に適切な条項を定めることで対策可能だが、その重要性はあまり知られていない。
章とトピック
- 株式会社と合同会社の比較と合同会社のデメリット概要
講師は、ビジネスの税金について解説する税理士チューバーである広野より氏。本講義では、株式会社と合同会社のどちらが良いか、特に合同会社の意外に知られていない3つのデメリットに焦点を当てて解説する。これから起業する人、あるいは個人事業主から法人なりをしたいと考えている人向けの内容である。なお、法人の設立をしようかどうか未だ悩んでいるという方は、過去動画や講師の著書が参考になるため、ぜひ参照することが推奨される。
- 株式会社と合同会社は税金の計算方法が基本的に同じである。
- コストをかけずにサクッと作りたいのであれば合同会社が一択である。
- 信用力重視であれば株式会社が一択である(合同会社に信用がないわけではない)。
- 合同会社には大きく分けて3つのデメリットがある。
- 株式会社と合同会社の詳細比較
株式会社と合同会社を比較表を用いて詳細に解説。合同会社は英語でLimited Liability Company (LLC) とも呼ばれる。実際の法人設立においては、合名会社や合資会社は倒産時の責任の範囲に限度がない無限責任であるため設立は非常に稀であり、株式会社と合同会社が最もメジャーな選択肢である。
- 定款認証: 株式会社は必要(費用は最低3万円でマックス5万円)、合同会社は不要(定款作成は必要だが認証は不要)。
- 登録免許税(国税): 資本金の7/1000。株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円。
- 会社設立時のコスト: 司法書士手数料を含め、圧倒的に合同会社の方が割安である。
- 出資意思決定: 株式会社は所有と経営の分離が基本で、意思決定は出資割合に応じた議決権(株式を多く持つ者に権限が集中)。日本の株式会社の99%は中小企業であり、所有と経営が分離されていないオーナー企業がほとんど。合同会社は出資者イコール役員が大前提で、意思決定は出資割合に関係なく完全合議制(一人一票)。これが合同会社の最大のデメリットの一つである。
- 代表者の名称: 株式会社は代表取締役、合同会社は代表社員(平役員は社員)。「代表取締役」という響きから株式会社の方が圧倒的人気がある。
- 役員の任期: 株式会社は最長10年(任期が来ると登記費用や司法書士手数料が再度発生)、合同会社は任期なし。合同会社は任期がないため、任期更新に伴う登記費用や司法書士手数料が再度発生しない点でコスト的に有利である。
- 株式の公開(上場): 株式会社は可能、合同会社は不可(株式という概念がないため)。将来上場を視野に入れているベンチャー企業は合同会社で設立すべきではない。
- 信用力: 株式会社の方が高め、合同会社はやや低め(合同会社を知らない人も一定数いるため)。
- 決算広告義務: 株式会社はあり(官報などでの開示義務があるが、中小企業で実行しているところはほとんどない。上場を考えている会社のみ実行されているのが現状)、合同会社はなし。
- 設立コスト削減策と合同会社の主要デメリット
設立コストを大幅に引き下げる特例として「特定創業支援等事業」が紹介された。これにより登録免許税が半額になる。また、合同会社の主要なデメリットの一つである「一人一票の完全合議制」について詳しく解説された。
- 設立コスト削減策(特定創業支援等事業): 創業5年未満の個人に限り、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を設立する際、登録免許税が1/2軽減される特例がある。これにより、株式会社は15万円が7.5万円に、合同会社は6万円が3万円に半額になる。この特例を受けるには、特定創業支援事業の認定を受けている市区町村で4回ほどの研修(費用はせいぜい1万円から2万円程度)を受け、認定を得て、その市区町村で会社を立ち上げる必要がある。この制度は、間もなく起業したい人にはタイミング的に難しい場合があるが、これからじっくり創業を考えていく人には活用を推奨される。
- 合同会社の主要デメリット1: 一人一票の完全合議制であること。一人会社や夫婦での設立であれば問題ない場合が多いが、友人や知人と会社を設立する場合に問題となる。例えば、2人で合同会社を設立する場合、出資比率が99%と1%であっても、会社の意思決定は完全に1対1の合議制となる。
- 合同会社のデメリット三選
合同会社には主に3つのデメリットがある。1つ目は「1対1の完全合意制」であり、意見が対立すると会社経営が滞る。2つ目は「非常勤役員の概念がない」ため、配偶者などを非常勤役員にしても社会保険加入が必須となる。3つ目は「社員(役員)の死亡は退社扱い」となり、一人会社の場合は解散、複数会社の場合は実質的な乗っ取りにつながる可能性がある。これらのデメリットを把握し、許容できる場合は合同会社、面倒だと感じる場合は株式会社での設立が推奨される。
- 合同会社は1対1の完全合意制。
- 合同会社には非常勤役員の概念がない。
- 合同会社の社員(役員)の死亡は退社扱い。
- 合同会社の設立費用は6万円あるいは3万円と安価。
- デメリットを許容できるなら合同会社、面倒なら株式会社がおすすめ。
- 1対1の完全合意制
合同会社は1対1の完全合意制であるため、意見が対立すると会社経営が全く進まなくなる。特に友人3人で会社を設立した場合、もし1人が残り2人の結託により実質的に会社を乗っ取られるような状況になる可能性がある。赤の他人と会社を運営していく場合は、合同会社ではなく株式会社の方が推奨される。定款によって社員ごとの議決権の割合を変えることはできるが、合同会社は所有と経営が完全に一致しているため、出資割合よりも社員同士の人間関係が最も重視される。株式会社の場合は役員の任期が来れば退任となるが、合同会社には任期がないため、他の役員に辞めてもらうことが不可能であり、これが足枷となる。
- 合同会社は1対1の完全合意制。
- 意見対立で会社経営が滞る。
- 友人3人で設立の場合、1人が残り2人の結託で会社乗っ取りに近い状態になるリスクがある。
- 赤の他人と会社を運営するなら株式会社がおすすめ。
- 合同会社は所有と経営が完全に一致している。
- 合同会社では出資割合よりも社員同士の人間関係が一番重視される。
- 非常勤役員の概念がない
合同会社には非常勤役員の概念がないため、配偶者が非常勤役員として就任しても社会保険への加入が必須となる。株式会社の非常勤役員は社会保険加入が不要であるのに対し、合同会社では絶対に入らなければならない。配偶者を役員とし、役員報酬を支給することで所得分散による節税効果が得られるが、合同会社では非常勤役員の概念がないため、社会保険加入が必須となり、この節税対策が基本的にはできない。これは、株式会社の代表取締役や取締役が所有と経営の分離を前提としているのに対し、合同会社の代表社員や社員は所有と経営が一致しており、出資者全員が業務執行権を持つ前提であるため、非常勤の概念が存在しないという立法趣旨がある。対策としては、株式会社化するか、使用人として労働時間を制限する(年収106万/130万未満、週20時間未満など)方法があるが、これらは手間がかかる。もう一つの方法として、定款変更により業務執行社員以外の社員(出資のみを行う者)とすることで、法人税法上の「みなし役員」規定を適用し、社会保険加入不要で役員報酬の支給を可能にする方法があるが、これは非常に面倒である。
- 合同会社には非常勤役員の概念がない。
- 配偶者が非常勤役員として就任しても社会保険加入が必須。
- 株式会社の非常勤役員は社会保険加入不要。
- 合同会社は所有と経営が一致し、出資者全員が業務執行権を持つ前提。
- 非常勤役員は存在しないという立法趣旨がある。
- 対策1: 株式会社化。
- 対策2: 使用人として労働時間制限(年収106万/130万未満、週20時間未満)。ただし、出勤簿作成など手間がかかる。
- 対策3: 定款変更で業務執行社員以外の社員(出資のみ)とし、みなし役員規定を適用。社会保険加入不要で役員報酬支給可能。ただし、非常に面倒。
- 役員報酬を年間130万いかないように設定することで社会保険加入対象外となる節税対策があるが、合同会社では基本できない。
- 社員(役員)の死亡は退社扱い
合同会社では社員(役員)の死亡は退社扱いとなり、出資の払い戻しとなる。一人会社の場合、自分が亡くなると会社が解散してしまう。これは法定退社事由である。2人以上の会社であれば解散とはならないが、亡くなった社員の相続人は合同会社に対して持ち分の払い戻しを請求するだけで、会社に関する権限は一切持たない。これにより、友人2人で会社設立した場合、自分が亡くなると実質的に合同会社がその友人相手のものになってしまう。対策としては、定款に「相続人が持ち分を承継する旨」を定めることで、死亡した社員の持ち分を承継し、相続人が社員として加入することが可能となる。この記載がないと、一人会社は解散、複数会社は乗っ取りを防ぐことができない。また、誰が会社を引き継ぐかについては遺産分割協議や遺言書で明確にしておくことが重要である。講師自身も数年前に合同会社を設立したが、この事実を知ったのは設立後であり、慌てて司法書士に確認したところ、定款に記載済みであったため安心したという経験を語っている。
- 合同会社では社員の死亡イコール退社。
- 死亡した社員の出資は払い戻しとなる。
- 一人会社の場合、代表者の死亡は会社の解散事由となる。
- 複数人の会社の場合、相続人は経営権を持たず、払い戻し請求のみ。
- 対策: 定款に「相続人が持ち分を承継する旨」を定める。
- 定款記載例: 「社員が死亡した場合は当該社員の相続人が当該社員の持ち分を承継して社員となることができる」。
- 遺産分割協議や遺言書で、誰が会社を引き継ぐかを明確にすることが重要。
提案
- 「もう間もなく起業したいんだという方はタイミング的に難しいかもしれませんが、これからじっくり創業を考えていくという方であれば、ぜひこちらを併せてご活用ください。」
- 「BtoBのビジネスではないBtoCの事業をやるとか上場会社ともお付き合いがないという方であればお気軽に合同会社を作っていただいたらいいんですけれどもやはりこの完全合規制というところその他様々なデメリットがあるんですね」
- このデメリット3つを把握していただいてそれぐらいのデメリットであればカバーできるという方は合同会社をお勧めします。
- これ面倒くさいなとやってられへんなという方は、株式会社でスタートされることをお勧めしたいと思います。
- 赤の他人さんと会社応用して行かれるという方は合同会社ではなく株式会社の方をお勧めしたいと思います。
- 非常に面倒いという方はやはり株式会社などその他の方法をお勧めしたいと思います。
- 年収が106万とか130万未満であるとか所定労働時間が週で20時間未満とかこういった制限を超えてしまうとやっぱり社会保険加入必須ということになりますのでご注意ください。
- 定款に相続人が持ち分を承継する旨を定めることによって、死亡した社員の持ち分を承継して、相続人が社員として加入することが可能。
- 皆さんはくれぐれもご注意いただきたいんですがこのような記載例ですこれを定款に入れておいてください社員が死亡した場合は当該社員の相続人が当該社員の持ち分を承継して社員となることができるこれを入れてもらえれば一人会社の方は会社の解散を防ぐことができます複数で会社運用されている方は乗っ取りを防ぐことができます。
- 遺言書でこの会社の持ち分に関してはどの子に相続させるとか、あるいは配偶者に相続させる。こういったところを明記しておいていただくと、併せてこの出資株の証券もスムーズにいくと思います。