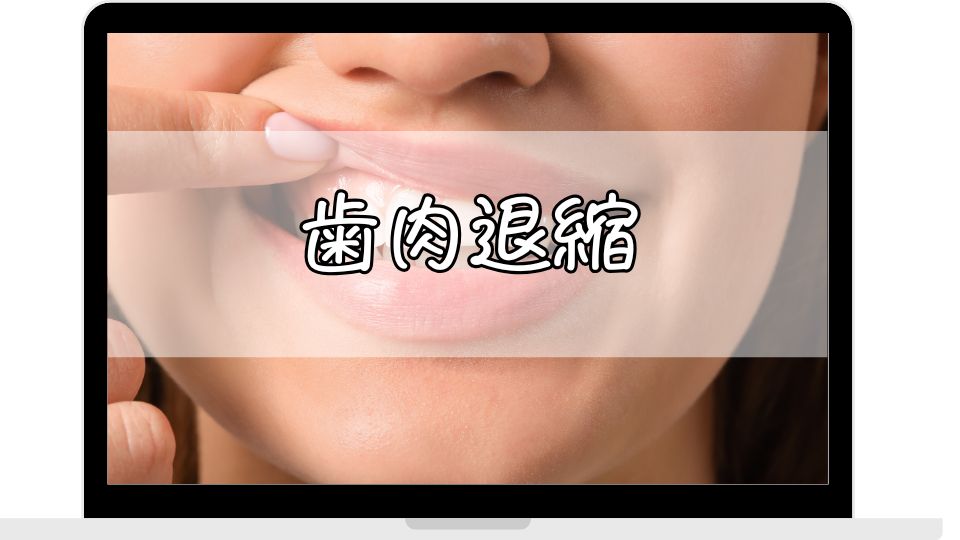この講義では、死肉退縮の原因と影響について、東洋医学と西洋医学の視点から解説されました。骨と死肉の厚み、血流、体温、ストレス、歯磨きの影響が取り上げられ、メイナードの分類に基づくタイプ分けも紹介されました。さらに、歯と歯茎の境界のケア方法や歯の矯正による骨の影響、上顎の死肉の再生能力についても説明されました。
要点
- 死肉退縮の原因
- 東洋医学と西洋医学の視点
- 骨の厚みと死肉の関係
- 実証と虚証の概念
- 血流と体温の関係
- メイナードの分類
- 歯磨きの影響
- 歯と歯茎の境界のケア方法
- ストレス性の食いしばりと歯ぎしりの影響
- 歯の矯正による骨の影響
章とトピック
死肉退縮の原因
死肉退縮は、歯茎が下がって歯の根っこが露出する現象で、骨の厚みや死肉の厚みによって影響される。
- 要点
- 骨がしっかりしていると死肉退縮は起こりにくい。
- 死肉の厚みがあると血流が良く、体温が高い。
- 血流が悪いと死肉が薄くなり、冷え性になる。
- 説明
死肉退縮は骨と死肉の厚みによって異なり、骨が厚く死肉も厚い場合は退縮しにくい。血流が良いと赤血球がスムーズに流れ、体温が高くなるため、死肉が厚く保たれる。
東洋医学と西洋医学の視点
東洋医学では実証と虚証、熱症と寒症の概念を用いて死肉退縮を説明し、西洋医学ではメイナードの分類を用いる。
- 要点
- 実証の人は骨がしっかりしており、死肉退縮しにくい。
- 虚証の人は骨が薄く、死肉も薄くなりやすい。
- メイナードの分類では、骨と死肉の厚みによって4つのタイプに分類される。
- 説明
東洋医学では体質や精神的な強さを基に死肉退縮を説明し、西洋医学では骨と死肉の物理的な厚みを基に分類する。これにより、個々の体質や生活習慣に応じたアプローチが可能となる。
メイナードの分類
メイナードは骨と死肉の厚みに基づいて4つのタイプに分類し、歯茎が下がりやすいかどうかを評価する。
- 要点
- タイプ1: 骨も死肉も厚い。
- タイプ2: 骨が厚く死肉が薄い。
- タイプ3: 骨が薄く死肉が厚い。
- タイプ4: 骨も死肉も薄い。
- 説明
この分類により、遺伝的要因や生活習慣による影響を考慮し、歯茎の健康状態を評価することができる。タイプ1が最も歯茎が下がりにくく、タイプ4が最も下がりやすい。
歯と歯茎の境界のケア方法
歯と歯茎の境界を適切にケアする方法についての説明。
- 要点
- 鏡を使って歯と歯茎の境界を確認する。
- 爪の生えているところに歯ブラシを当てて練習する。
- 感覚を頼りにして歯ブラシを使う方法を習得する。
- 説明
爪の生えているところに歯ブラシを当てて、痛くなく心地よい速度と圧力で練習し、その感覚を歯と歯茎の境界に応用する。
ストレス性の食いしばりと歯ぎしりの影響
ストレスによる食いしばりや歯ぎしりが歯と歯茎に与える影響についての説明。
- 要点
- 歯の根の部分はしっかり埋まっているため壊れにくい。
- 頭の部分が揺さぶられると境界線が破壊される。
- 歯茎が下がるのではなく、歯が壊れる現象が起こる。
- 説明
ストレスによる食いしばりや歯ぎしりが歯の境界線を破壊し、歯が壊れる現象を引き起こす。
歯の矯正による骨の影響
歯の矯正が骨に与える影響についての説明。
- 要点
- 人工的に歯を外側に出すと骨の壁を超越する。
- CTを使って事前に骨の状態を確認する。
- 再生治療を行うことで歯茎の下がりを防ぐ。
- 説明
矯正前にCTで骨の状態を確認し、必要に応じて再生治療を行うことで、歯茎の下がりを防ぐ。
上顎の死肉の再生能力
上顎の死肉が再生する能力についての説明。
- 要点
- 上顎の死肉は再生する臓器である。
- 上顎の死肉を移植すると元に戻る。
- 上顎の死肉は取っても取っても戻る。
- 説明
上顎の死肉は再生能力が高く、移植しても元に戻るため、歯茎が下がった場合の治療に利用できる。
歯肉移植の技術とその効果
歯肉移植の技術とその効果についての説明。
- 要点
- 上顎の死肉を移植して歯茎を再建する。
- 移植によって見た目もきれいにできる。
- ペリオドンタルプラスチックサージョンという分野がある。
- 説明
上顎の死肉を移植することで、歯茎の見た目を改善し、再建することができる。
東洋医学と西洋医学のアプローチの違い
東洋医学と西洋医学のアプローチの違いについての説明。
- 要点
- 東洋医学では未病治療を重視する。
- 西洋医学では技術的な治療を行う。
- ストレスや歯磨きの仕方が影響する。
- 説明
東洋医学では未病治療を重視し、ストレスや歯磨きの仕方が歯茎に与える影響を考慮する。